カチッサー効果とは
カチッサー効果(Automaticity)とは、正しいかどうか分からない働きかけであっても、深く考えることなく無意識に反応してしまう心理効果のこと。
提唱者であるハーバード大学エレン・ランガー教授の以下の実験が有名です。
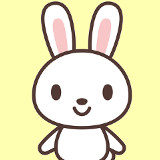
人間って意外とあんまり考えずに、それっぽく反応してるよね・・。

うさぎに言われたくないよ!
理由という名の「働きかけ」

ここでは、カチッサー効果を調査したエレン・ランガー教授の実験についてご紹介します。
ある図書館にコピー機の順番を待つ数人の列がありました。
この時、列の一番先頭で待つ人に、先にコピー機を使わせてくれないかとお願いをする実験です。
そして、そのお願いの仕方は3パターンを準備します。
お願いの仕方でコピー機の順番を譲ってくれる割合はどう変化するのでしょうか。
お願いの仕方1:
「すみません、5枚だけ先にコピーをとらせてもらえませんか?」
(要求のみを伝えるお願い)
→ お願い成功率 60%
お願いの仕方2:
「すみません、急いでいるので5枚だけ先にコピーをとらせてもらえませんか?」
(理由を付与したお願い)
→ お願い成功率 94%
お願いの仕方3:
「すみません、コピーをとらなければいけないので5枚だけ先にコピーをとらせてもらえませんか?」
(よく分からない謎の理由を付与したお願い)
→ お願い成功率 93%
上記の結果から、2つのことが分かります。
1.何か他人にお願いをするときは、理由を付けるとOKを貰いやすい。
2.たとえ正しいかどうか分からない謎の理由であってもOKを貰いやすい。
お願いごとになにかの理由(働きかけ)が付け加えられていた場合、相手は深く考えることなく無意識に反応し、承諾してしまうとエレン・ランガー教授は自身の論文で綴っています。
そして、たとえ正しいかどうか分からない謎の理由(働きかけ)であっても、人間は反応してしまうわけです。
カチッサー効果のメカニズム
カチッサー効果は、人間の認知プロセスに関する一つの側面を浮き彫りにします。
人々は日常生活で多くの情報にさらされていますが、全ての情報を詳細に検討することは困難です。そのため、脳は効率的に情報を処理するために、シンプルな判断基準やパターンを使用します。
カチッサー効果は、この脳の処理方法に基づいています。
相手のお願いに理由という働きかけが付与されていれば、脳はそれだけでOK判断とみなしてしまうわけです。
身の回りにあるカチッサー効果の例

例えば、私たちが普段スーパーマーケットやオンラインショッピングで買い物をするときにも、カチッサー効果を発動させる「働きかけ」が潜んでいます。
商品に「大人気」というラベルがついていると、無意識にその商品が価値があると判断しやすくなります。このラベルが「働きかけ」となってカチッサー効果を引き起こし、商品を購買する意欲が高まる可能性があります。
商品に「自慢の一品です」という店主の手書きポップがあった時も同じように、カチッサー効果が発動します。たとえ「なぜ自慢の一品」なのかということについて一切説明がない謎の状態であってもです。
カチッサー効果は、マーケティングや広告、影響力のあるコミュニケーションに広く利用されています。企業はこの現象を理解し、消費者の行動を誘導する戦略を構築しています。
また、SNSの通知やアプリの操作画面におけるデザインも、カチッサー効果を利用しています。
(参考文献)
Langer, E. J. (1989). Mindlessness as Maladaptive Persuasion. Journal of Personality and Social Psychology




コメント