コブラ効果とは
コブラ効果(Cobra effect)とは、問題を解決しようとしたにも関わらず、逆に問題を悪化させてしまう「意図せざる結果」になってしまうことを示した教訓のこと。
イギリス統治時代のインドでの逸話をもとに、ドイツの経済学者ホルスト・シーバートによって造られた言葉です。

問題を解決しようとしたのに悪化してしまうって・・

人類はいろんな教訓を残してくれてるんだね♪
減らすつもりが、逆に増えてしまう。

インドを統治していた英国のインド総督府は、街や村に猛毒を持つ毒ヘビ、コブラが大量に生息していることに頭を悩ませていました。
そこでインド総督府は、コブラの死骸を役所に持ち込んだ人々に報奨金を出すことにしました。街の人々がコブラを捕獲することで、街からコブラの脅威を排除する作戦でした。
最初はこの作戦が上手く機能し、街の人々は一生懸命コブラを捕獲するようになりました。
しかし、報奨金のためにコブラを大量に飼育し始める人たちが現れ、この作戦は機能しなくなったのです。
よって、インド総督府は報奨金制度を廃止し別のやり方を考えていましたが、報奨金制度が無くなったことで、コブラを飼育していた人々が用済みになった大量のコブラを野に放ってしまいました。
結果として、コブラを減らすための作戦が、コブラを増やしてしまうことになってしまいました。
ハノイのネズミ問題
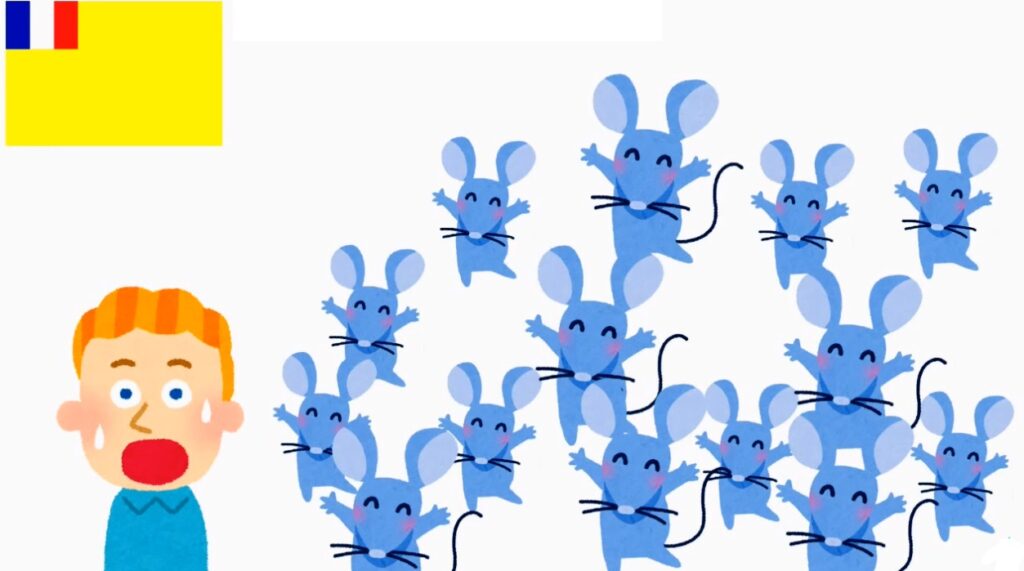
歴史家マイケル・ヴァンによると、上記のコブラの事例は明確な記録が存在しないが、1902年にベトナムのハノイで発生したネズミの駆除の「意図せざる結果」の事件が歴史上存在するため、同様の効果を「コブラ効果」ではなく「ラット効果」と呼ぶべきだと主張しています。
1902年「ハノイのネズミ大駆除」
当時、ペストの原因がネズミであることが分かり、ハノイ保健当局にとって街の大量のネズミが悩みの種でした。そして、ネズミの駆除をした人々に報奨金を出すやり方を進めました。駆除した「ネズミのしっぽ」を役所に持ち込むとお金と交換できる仕組みだったのですが、民衆は捕獲して駆除するぐらいなら、しっぽだけを切り落として、飼育してしまえば多くの報奨金を得られると考えました。結果、街にはしっぽのないネズミが大量に発生し、この作戦は失敗に終わりました。
なお、もう1つ「意図せざる結果」について触れた記事を過去にアップしています。こちらも併せてご覧ください。
報酬を出す対象を見誤る

シカゴ大学ビジネススクールのアイエレット・フィッシュバック教授は「報酬を出す対象」を見誤ると、意図した行動とは違う行動が生まれてしまい「意図せざる結果」が引き起こされると指摘しています。
上記のデリーやハノイの例を見ても、民衆は報酬によって行動を変容させています。
その行動が「駆除する」ではなく、「飼育する」だったのが残念なところですが、報酬は決して意味のないものではなく、確かに人を動かします。
私たちの日常やビジネスでも、インセンティブやご褒美を相手に与えることがあります。
「意図せざる結果」が引き起こされないよう、フィッシュバック教授は2つの問いで報酬をチェックする必要があるとしています。
1.
その報酬は目標に向けた進捗を促すか。
ただ測定しやすいだけで、あまり意味のない指標を掲げてはいないか。
2.
その報酬を達成する一番簡単な方法はなにか。どんな近道や抜け道があるか。
最短ルートが目標に貢献しないものであれば、それは間違った報酬である。
(参考文献)
アイエレット・フィッシュバック「ネズミ駆除対策がかえって大量発生を招いた訳」東洋経済オンライン(2023)





コメント