ブーバ・キキ効果とは
ブーバ・キキ効果(Bouba/kiki effect)とは、特定の音を聞いたり、言葉を見たりすると、それに対応する形状や物体を想像する傾向がある現象です。
この効果は、1930年代にドイツの心理学者ヴォルフガング・ケーラーによって報告され、アメリカの神経科学者ラマチャンドランによって命名されました。
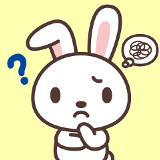
音と形がリンクするっていうこと?

こちらの実験をごらんください。
どっちがブーバで、どっちがキキ?

ブーバ・キキ効果を示した有名な実験があります。
実験参加者に「ブーバ」(Bouba)と、「キキ」(Kiki)という2つの単語を伝え、この上の図形のどちらが「ブーバ」でどちらが「キキ」なのかを答えてもらう実験です。
すると驚くべきことに、98%の人が「ブーバ」を丸い形状と関連付け、「キキ」を尖った形状と関連付けるという結果が得られました。
この効果は、言葉の音響的特性と形状の視覚的特性が、私たちの脳内で結びついていることを示唆しています。
ブーバ・キキ効果のメカニズム
ブーバ・キキ効果の背後にある主要な科学的原理は、音響と視覚情報の結合です。
言葉の発音には音の高さや音の質が含まれます。例えば、「ブーバ」のような音は柔らかく丸い音に聞こえますが、「キキ」のような音は鋭く尖った音に聞こえます。
一方で、形状や物体には丸いものと尖ったものがあります。
私たちの脳は、これらの音の特性を視覚情報と結びつけ、一貫性を持たせることを好むようです。そのため、「ブーバ」という音が丸い形状と関連付けられるのです。
応用と興味深い事例

ブーバ・キキ効果は、デザインやマーケティングの分野で広く活用されています。
基本的に角ばった物よりも丸みを帯びた形状のほうが、フレンドリーな印象を与えやすいと言われています。言われてみると、Amazonのサイトにある「今すぐ購入」ボタンや「カートに入れる」ボタンなどは全て丸みを帯びたものになっています。
また、製品やブランドのロゴデザインにおいて、音のイメージと形状の一致を利用して、消費者に強い印象を与えることができます。
また、この効果は言語学や神経学の研究にも重要な示唆を与えています。
脳が言葉と形状をどのように結びつけ、認識するのかを理解するために、ブーバ・キキ効果の研究は続けられています。
脳にも好みがあるみたい
ブーバ・キキ効果は、言葉と形状の不思議な結びつきを示す興味深い現象です。
これは私たちの脳が音響的特性と視覚的特性を結びつけ、一貫性を持たせようとする結果として起こるものです。
この効果はデザインや言語学など多くの分野で応用され、私たちの知識や文化に深い影響を与えています。
(参考文献)
真壁昭夫「イラスト&図解知識ゼロでも楽しく読める!行動経済学のしくみ」西東社(2022)




コメント