泥棒洞窟実験とは
泥棒洞窟実験(The Robbers cave experiment)とは、楽しいことよりも困難を共有したほうが、信頼関係が深まることを明らかにした実験のこと。
1954年、トルコ系アメリカ人の社会心理学者ムザファー・シェリフがこの実験を実施し、その現場のキャンプ場の名前にちなんで泥棒洞窟実験と名付けられました。
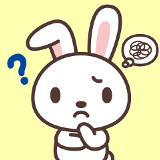
楽しいことを共有したほうが、仲良くなれるんじゃないの?

共通の困難に力を合わせて立ち向かった。こっちほうが結束を高めるよ。
楽しいことよりも困難を共有する

思春期の少年たちを集め、3週間に渡り実験は行われました。
まず、下準備として2つのグループに分け、自然とこの2つのグループが対立するような仕掛けをします。
(仕掛け例)
・意図的に自グループ内の結束を高めるような催しをする
・片方のグループにだけ賞品が出るゲームを開催する
・誤って相手グループの野球場で野球をしてしまうように仕向ける
思春期真っ只中の2グループが「なんなんだよアイツら・・」と敵意むき出しになったところで実験スタート。
この時点では、多くの少年が自グループのことを肯定的に捉える一方で、相手グループのことを否定的に捉えていました。この集団間の対立を「集団間葛藤」と言います。
さて、この2グループを仲良くさせるために、どんなことをすべきでしょうか。
1.花火を使ってわいわい楽しく交流の場を設ける。
2.一緒に壊れた水道管を修理する課題を与える。
シェリフは、2の「一緒に壊れた水道管を修理する課題を与える」ことで、相手グループへの好意が生まれ、関係性に改善が見られたと報告してます。
つまり、楽しいことの共有よりも困難を共有したほうがお互いの信頼関係は深まるということです。
共通の課題があると結束できる
お互いの協力なしでは解決できないような共通の課題を目の当たりにしたとき、2つのグループは団結することができるというわけです。
目標を達成するために相手グループは「役に立つ」存在であるため、否定的な考えよりも肯定的な考えが生まれるメカニズムと言われています。
なお、このような相手の協力が必要な共通の目標のことを、上位目標(Superordinate Goals)と言います。上位目標の存在で、2つのグループはまとまることができました。
また、会社に嫌いな上司がいることがきっかけで同僚と仲良くなれた!という現象を経験したこともあるのではないでしょうか。いわゆる「共通の敵」というものですね。
これは、共通の課題によって同僚の間で「一体感」が生まれるからです。
(参考文献)
Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W.(1961)Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment. University of Oklahoma




コメント